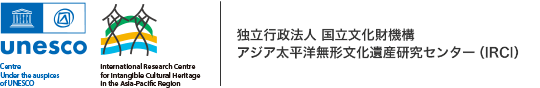イベント
2024年11月21日
国際シンポジウム「持続可能なまちづくりと無形文化遺産-アジア太平洋地域における文化遺産の統合的保護の視点」および関連イベントを京都で開催しました(2024年10月10日~12日)
「無形文化遺産の持続可能な開発への貢献に関する調査研究-持続可能なまちづくりと無形文化遺産(2022~2024年度)」事業における最終シンポジウム「持続可能なまちづくりと無形文化遺産―アジア太平洋地域における文化遺産の統合的保護の視点」を、2024年10月11日(金)に京都で開催しました。
シンポジウムは、2件の基調講演と4件の事例報告で構成されました。基調講演では、アナニャ・バタチャリャ氏(コンタクトベース)はインドの世界文化遺産サンティニケタンにおける無形文化遺産の実践と遺産観光に焦点を当て、清水重敦氏(京都工芸繊維大学)は宇治茶の文化的景観とその遺産価値を維持する上での課題について話されました。事例報告では、カンボジア・アンコール地域における籐工芸品の生産、マーシャル諸島における海洋景観と伝統的航海術、マレーシア・ジョージタウンの文化遺産フェスティバルなど、本事業で実施した調査結果の報告およびキルギスにおけるコミュニティ中心の伝統的知識保護の取り組み事例について発表が行われました。最終討論では、世界遺産条約と無形文化遺産保護条約の方向性の違いを再認識した上で、有形・無形の遺産の相乗効果と相互関連性、および遺産の統合的保護と管理における無形文化遺産の積極的な役割を中心に議論しました。特に、コミュニティの遺産保護に無形文化遺産を活用する上で、システムとしての遺産の統合的理解が重要であり、遺産を隔てるカテゴリー化から脱却しなければならないことが強調されました。文化遺産が人々を結びつけアイデンティティに貢献していることを踏まえ、新たな課題に絶えず対応し、文化遺産に新たな意味を持たせていくことの重要性が強調されました。また、世界遺産条約で強調される真正性(オーセンティシティ)の概念について、コミュニティの視点および無形文化遺産の枠組みにおいて再検討する必要性があることも提起されました。
本シンポジウムには、事業関係者、発表者、無形文化遺産研究者、大学院生など約50名が参加しました。ユネスコ・カテゴリー2センターである韓国のアジア太平洋無形文化遺産国際情報ネットワークセンター(ICHCAP)とモンゴルの国際遊牧文明研究所(IISNC)からの専門家もオブザーバーとして参加しました。
シンポジウム前日の10月10日には、2022年度以来カンボジア、マレーシア、マーシャル諸島で実施してきた事例研究の成果を共有し、事業の最終成果について議論するための関係者会議を開きました。また、シンポジウム翌日の10月12日には、同志社女子大学現代社会学部大西秀之教授担当のプロジェクト演習との協力によりエクスカーションを実施しました。京都の無形文化遺産がどのように保護・活用されているか、学生たちの視点で4つのテーマを選択しました。参加者は2つのグループに分かれ、コースAでは庭園の音風景とマンガ・アニメ文化について体験し、コースBでは伏見における水の役割、御朱印集めと寺社観光について探索しました。エクスカーションの模様は同志社女子大学のウェブサイトでも紹介されました。
なお、シンポジウムの様子は、後日、IRCI公式YouTubeチャンネルで公開予定です。
関係者会合と最終シンポジウムでの議論を踏まえ、本事業の最終報告書を2025年3月に刊行する予定です。

バタチャリャ氏による国際シンポジウム基調講演の様子

国際シンポジウム最終討論の様子

10月10日の事業関係者会議の様子

エクスカーションの様子(御香宮神社(京都市伏見区))